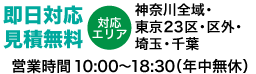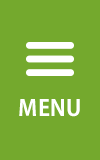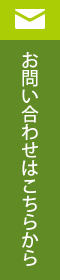【横浜市】死亡後の手続きまとめ
横浜の遺品整理 想いてです。
横浜市でご家族が亡くなった際、気持ちが落ち着かない中で、同時に多くの手続きを行わなければならないことに戸惑う方は少なくありません。
死亡届の提出をはじめとして、保険証や年金の手続き、銀行口座の凍結や保険金の請求、さらには遺品整理や相続の準備など、期限付きの手続きが次々と発生します。
特に、役所関係の届け出や必要書類の準備には、「何から始めたらいいのかわからない」「どこに問い合わせればいいのか不安」といった声も多く聞かれます。
また、最近ではスマートフォンやパソコンなどの“デジタル遺品”の対応も、見落とされがちなポイントです。
この記事では、横浜市での死亡後の手続きを時系列でわかりやすくご紹介しながら、遺品整理に向けた準備や注意点についても解説していきます。
大切な方を亡くされた後の不安や負担を少しでも軽くできるよう、丁寧に情報をお伝えしていきます。
目次
死亡後に必要な主な手続きの流れ

大切なご家族が亡くなられた後、遺された方は悲しみの中でも多くの手続きを行う必要があります。
限られた時間の中で複数の手続きを進めることは、精神的にも大きな負担となります。
だからこそ、手続きには優先順位をつけ、段階的に対応していくことが重要です。
手続きは「期限」「優先度」で分けて考える
死亡後の手続きは、「いつまでに」「どこに」行うかを明確にしておくことで、落ち着いて対処しやすくなります。
まず最優先で行うのが「死亡届の提出」と「火葬許可証の取得」です。
これらは火葬や葬儀を行うために必要不可欠で、死亡の事実を知った日から7日以内という提出期限があります。
その後は、健康保険証や介護保険証の返却、年金の受給停止手続き、生命保険の請求、銀行口座の凍結など、契約関係の手続きが続きます。
さらに、相続や不動産の名義変更といった専門性の高い手続きへと移行していきます。
このように、手続きを期限順・重要度順に分けてリスト化することで、遺族の精神的な負担を少しでも軽減することができます。
まずは死亡届と火葬許可証(横浜市区役所)
死亡届は、医師が作成する「死亡診断書」とともに、横浜市内の各区役所戸籍課に提出します。
提出するのは、亡くなられた方の本籍地・住所地・死亡地いずれかを管轄する区役所です。
提出期限は死亡の事実を知った日から7日以内と法律で定められています。
届け出を済ませると、火葬や埋葬に必要な「火葬許可証」が発行されます。
葬儀社と連携して進めるケースも多いため、日程に余裕を持って準備を進めることが大切です。
横浜市内の各区役所の戸籍課窓口や受付時間については、以下の横浜市公式ページで確認できます:
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/todokede-touroku/koseki/shiboutodoke.html
健康保険・介護保険などの資格喪失手続き

死亡届を提出した後は、故人が加入していた各種公的保険に関する「資格喪失」の手続きを行う必要があります。
特に、健康保険証や介護保険証の返却は、市区町村での手続きが中心となり、窓口対応が必要な項目です。
保険制度によって手続き方法や担当部署が異なるため、内容を確認してから対応するようにしましょう。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の返却
亡くなられた方が「国民健康保険」または「後期高齢者医療制度」に加入していた場合、保険証の返却と資格喪失の届出を行う必要があります。
これらの手続きは、横浜市内の各区役所の保険年金課が窓口となっています。
手続きには、死亡届の控えや保険証の原本、届出人の本人確認書類などが必要となります。
特に後期高齢者医療制度の場合は、保険料の還付が発生することもあるため、口座情報を準備しておくとスムーズです。
各区の担当窓口や受付時間は、以下の横浜市公式ページから確認できます。
※「○○区 保険年金課」と検索することで、該当するページを見つけることができます
https://www.city.yokohama.lg.jp/
なお、故人が会社員だった場合(健康保険組合や協会けんぽ加入者)の場合は、勤務先または保険組合への連絡が必要となり、市役所での手続きは不要です。
介護保険証の返却とサービス停止
介護保険の要介護認定を受けていた方が亡くなられた場合は、「介護保険証」の返却が必要です。
こちらも各区の保険年金課または高齢・障害支援課が窓口となります。
返却時には保険証の原本と届出人の本人確認書類が必要です。
また、介護サービスを受けていた場合は、担当のケアマネジャーへの連絡と、デイサービス・訪問介護などのサービス事業所への解約の連絡も速やかに行う必要があります。
未使用分のサービス料返金などがある場合もあるため、事業所とのやり取りは丁寧に進めることが望まれます。
年金・保険・銀行口座の手続き

死亡後に必要な手続きには、年金や保険、銀行口座などの契約に関するものも含まれます。
これらは放置してしまうと金銭的なトラブルや不正使用のリスクにつながるため、できるだけ早めに対処することが大切です。
それぞれの手続き先や必要書類を確認し、計画的に進めていきましょう。
年金受給者だった場合の「年金受給停止届」
故人が国民年金または厚生年金の受給者であった場合、「年金受給権者死亡届(報告書)」を日本年金機構へ提出する必要があります。
これにより、年金の支給が停止されます。
提出は、年金事務所への郵送または窓口での手続きが可能です。
必要書類としては、年金証書や死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書の写しや除籍謄本など)、届出人の本人確認書類などが求められます。
注意したいのは、届出を怠ると故人宛てに年金が振り込まれ続けてしまい、後日返金手続きが必要になる点です。
受取口座の凍結前に早めの手続きを行うと安心です。
生命保険・医療保険などの請求
故人が加入していた生命保険や医療保険がある場合は、各保険会社に連絡し、保険金の請求を行います。
まずは手元にある保険証券を確認し、契約者情報・受取人・保障内容などを把握しましょう。
必要な書類は保険会社ごとに異なりますが、一般的には「死亡診断書」「保険証券の原本」「受取人の本人確認書類」「請求書類一式」などが必要です。
スムーズに進めるためにも、早めの問い合わせが推奨されます。
銀行口座・クレジットカードの停止
亡くなった方名義の銀行口座やクレジットカードは、死亡の事実を銀行やカード会社に通知することで利用が停止されます。
銀行口座については、死亡届提出後に金融機関へ「死亡届(銀行用)」を提出すると、口座が凍結され引き出しができなくなります。
なお、相続手続きが完了するまでは口座の凍結が解除されないため、通帳やキャッシュカードは相続人が責任をもって保管することが大切です。
預金の相続に備えて、残高証明や取引履歴の取得を早めに行っておくとよいでしょう。
このような契約関連の手続きも、早期に整理することで後々の相続や遺産分割が円滑になります。
次からは、遺品整理のポイントについて詳しく見ていきます。
遺品整理を始める前に

故人が亡くなられた後、部屋の片付けや持ち物の整理をいつ始めるべきか悩む方は多くいらっしゃいます。
遺品整理は、ただ物を処分する作業ではなく、故人との思い出に向き合う時間でもあります。
焦って手をつけると、後から「残しておけばよかった」と後悔してしまうこともあるため、始めるタイミングや進め方には注意が必要です。
故人の思いと遺族の気持ちを尊重する整理を
遺品整理は、気持ちの整理がある程度ついてから始めるのが理想です。
悲しみが癒えないうちに急いで片付けてしまうと、大切な思い出の品まで処分してしまう可能性があります。
まずは、故人の愛用品や記念品などを「形見分け」として親族間で分け合うことから始めましょう。
その上で、「残しておきたいもの」「一時的に保管するもの」「処分するもの」と分類すると、心情的な負担も少なく、整理がしやすくなります。
思い出が詰まった品物には、それぞれのご家族の想いがあります。
整理を進める中で意見が分かれることもありますが、故人を偲ぶ気持ちを共有しながら、丁寧に進めることが大切です。
相続トラブルを避けるために共有しておくべきこと
遺品の中には、高額な品物や現金、通帳、不動産関係の書類など、相続に関わる重要な財産が含まれていることがあります。
こうしたものを誰がどのように管理するかは、親族間であらかじめ共有しておくことが不可欠です。
たとえば、遺産分割協議が終わる前に故人の持ち物を勝手に売却・処分してしまうと、「相続財産を勝手に減らされた」としてトラブルの原因になることもあります。
特に、金銭的な価値のある美術品、貴金属、ブランド品、現金などの取り扱いには慎重になりましょう。
遺品整理を始める前に、「これは相続財産に該当するかどうか」「全員の同意が得られているか」を確認しながら進めることで、後々の揉め事を防ぐことができます。
横浜市で必要な手続き窓口まとめ

死亡後の手続きを円滑に進めるには、地域の行政窓口を正しく把握しておくことが重要です。
横浜市では、死亡届や保険証の返却といった戸籍関連の手続きから、遺品整理に伴う粗大ごみの申請、消費生活に関する相談まで、各分野に対応した窓口が設けられています。
ここでは、横浜市における主な手続き先をご紹介します。
各種手続き・返却などの窓口
- 死亡届の提出
死亡診断書と一緒に、横浜市内の各区役所の戸籍課に提出します。 - 保険証の返却
国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療制度に加入していた場合、保険証の返却を行います。
これらは保険年金課が窓口です。 - 介護保険証の返却
介護保険の要介護認定を受けていた方が亡くなられた場合は、「介護保険証」の返却が必要です。
各区の保険年金課または高齢・障害支援課が窓口となります。
-
「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出
国民年金または厚生年金の受給者であった場合、「年金受給権者死亡届(報告書)」を日本年金機構へ提出する必要があります。
年金事務所への郵送または窓口で提出します。 - 保険金の請求
故人が加入していた生命保険や医療保険がある場合は、各保険会社に連絡し、保険金を請求します。 - 銀行口座やクレジットカードの停止
死亡の事実を銀行やカード会社に通知します
ごみ・粗大ごみ・家電の処分(資源循環局など)
遺品整理の際に出る家具や電化製品などは、横浜市の「資源循環局」管轄で適切に処分する必要があります。
特に粗大ごみは、事前の申し込みが必要です。
申し込みはインターネットまたは電話で受け付けており、収集日はお住まいの地域によって異なります。
また、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などの家電製品は、家電リサイクル法に基づき、指定の方法で処分する必要があります。
横浜市ではこれらの家電を回収していないため、購入した店舗や指定引取場所への持ち込み、または横浜家電リサイクル推進協議会への申し込みが必要です。
詳細な処分方法や申し込み先については、以下のリンクをご参照ください。
エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の出し方:
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomi-recycle/gomi/shushufuka/kadenseihin/das9.html
デジタル遺品・各種相談窓口(横浜市消費生活総合センターなど)
最近では、スマートフォンやSNS、オンラインサービスといったデジタル遺品の扱いも重要な課題です。
SNSアカウントの削除やネットサービスの解約などに困った場合は、横浜市の「消費生活総合センター」で相談が可能です。
同センターでは、消費生活に関するさまざまな相談を受け付けており、専門の相談員が対応しています。
その他、契約トラブルや悪質商法の相談も受け付けており、高齢のご家族の名義で契約されていたサービスの確認や解約などの相談先としても活用できます。
横浜市消費生活総合センター: https://www.yokohama-consumer.or.jp/
まとめ|心と暮らしの整理を安心して進めるために

ご家族が亡くなられた後の手続きは、死亡届の提出をはじめ、保険や年金の届け出、銀行口座や契約サービスの停止、相続に関する調整など、多岐にわたります。
こうした手続きは、ただでさえ大きな喪失感の中で行うことになるため、精神的にも身体的にも大きな負担となることが少なくありません。
そんな時こそ、ひとつひとつの手続きを整理し、周囲のご家族や専門家と連携しながら、順を追って進めていくことが大切です。
特に遺品整理においては、単なる片付けではなく、「気持ちの整理」という意味合いも持っています。
無理に急がず、故人の思い出を大切にしながら、丁寧に向き合うことが望まれます。
また、すべてを家族だけで抱え込まず、第三者のサポートを活用することもひとつの選択肢です。
遺品整理や生前整理に関する知識と経験を持つ専門家に相談することで、負担を軽減し、安心して前に進むことができます。
横浜で遺品整理にお悩みの方は、遺品整理 想いてにぜひご相談ください。
経験豊富なスタッフが、ひとりひとりの思いに寄り添いながら、丁寧にお手伝いをいたします。
遺品整理はもちろん、生前整理や不用品の買取、相続・不動産のご相談まで幅広く対応しております。
あなたとご家族が、これからも安心して毎日を過ごせるよう、心を込めてサポートいたします。
遺品整理 想いて
・遺品整理士 在籍
・相続診断士 在籍
・終活カウンセラー 在籍
・遺品整理士認定協会 実地研修受講者 在籍
・遺品整理士認定協会 座学研修受講者 在籍